こんにちは!きったんです。今回は指定校推薦をおすすめする理由についてお話できればと思います。
その前に指定校推薦がネガティブにとらえられる理由についてお話します。
指定校推薦がネガティブにとらえられる理由
- 受験が早く終わり一般受験生からは羨ましく映る
- 受験から逃げたと思われる
- 授業態度が悪かったり、遊びに行きまくる人もいる
- 希望する大学が取れなかった
- 偏差値の低い高校からの生徒のレベルが低い
- 受験で入学していない
- 特に英語のレベルが低すぎる
といったように嫉妬、焦り、偏差値の高い大学になると一般受験組との学力的な差で馬鹿にする人がいる傾向があったりします。
でも正直これらについては気にすることはないと断言できます。
指定校推薦のメリット
- 推薦を受ければ合格に限りなく近い
- 受験費用が1大学1学部のみになり経済的
- 合格後は学業以外にもゆとりができる
といったメリットがあります。推薦を受け合格すると他の大学へ進路変更することはできなくなりますが、大学受験のための塾代や受験費用を抑え経済的で親御さんにも喜ばれたり、進路が決まると学業以外にも時間を割け、僕の周りではアルバイトを始め新生活に向けた資金を稼いだり、自動車免許の教習所へ通ったり、簿記やTOEICの勉強を始めたりと時間を有効活用する人もいました。
なので受験勉強に極力時間を割きたくない方にはメリットが大きいと思います。
指定校推薦を取るには?
通う高校や大学によって条件はバラバラではあるものの大体の学校で条件として挙げられるのが、以下5つとなってきます。
- 評定平均を上げる⇦行きたい大学は要確認
- 模試(進研模試が多い)の偏差値を上げる
- 課外活動で成果を上げる(部活動、ボランティア)
- 資格を取得する(漢検、英検、数検、簿記)
- 生活態度(出席率、校則遵守)
※評定平均は1年生からの積み重ねになるので継続して定期テストに熱を注ぐことが必要になるのと、各大学の求める評定平均を突破しないと門前払いになってしまうので推薦取るには評定平均を上げることは必須条件となります。
就活で指定校推薦は不利になるのか?
僕は大学をストレートで卒業し就職しましたが就職活動で不利になった就職活動で不利になったことはなかったです。
どういうことかというと、まず第一に就活で大学の入試方法について聞かれたことは一回もなかったです。しいていうならばSPIという学力試験みたいなものがあり面接前のエントリーシート段階でふるいにかけられるれたりと対策をしないとSPIや書類選考の時点で落とされ面接にたどり着けない状態に陥ります。学力に自信がない方は早めに対策する必要があります。
指定校推薦をなぜおすすめするのか
一般受験は学校の成績や生活態度は一切関係なく試験本番の一発勝負で、短期集中型の方が向いてるといえます。
一方、指定校推薦は学校生活での成績や生活態度が大きく影響し長期的な信用や努力が必要となります。
そこで指定校推薦をおすすめする理由ですが、高校3年生になって大学受験に本腰を入れて勉強をしライバルたちと競い合うのか、指定校推薦を目指し勉強に熱を入れてる人が少ない中1−2年から本気で勉強するのかといった状況だからです。整理すると、
一般受験=多くの勉強に本気になったライバルと勝負 or 指定校推薦=遊んでる人が多い中で自分を律し長期的に勉強
となります。
ライバルが少ない状態で戦える点や特に痛感したのが1ー2年生の時に受けた模試と3年生に受ける模試では偏差値のとりやすさが断然1ー2年生の方が簡単でした。そこで高偏差値をとり推薦をもらうために勉強しました。
💡特に私立文系の場合には日本史・世界史/古文・漢文が狙い目です。理由は世界史・日本史は暗記科目なので覚えるだけで点数が取れ、漢文・古文は単語の意味を覚えたり、慣用句や熟語を覚えると文章が読めるようになります。1−2年生時にはまだ勉強してるライバルが少ないので偏差値も上げやすいのでおすすめです。
ちなみに古文対策でおすすめの参考書は
以上が指定校推薦をおすすめする理由です。
さいごに
今回は指定校推薦をおすすめする理由についてお話ししましたが、これから高校生活を始める学生さんや、指定校推薦を目指すか悩んでいる方に参考になれば幸いです。
僕は幸い希望する大学に推薦がとれ目標達成でき、周りの同級生にあれだけ頑張ってたから取れて納得だと行ってもらえましたが、同時に俺も指定校目指して1ー2年生の頃から勉強しておけばよかったという同級生が多かったです。
知ってるか知っていないかでも高校生活が変わることにもなる可能性もあるので、自分がどういった高校生活を送りたいのかを考える材料になれば幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。




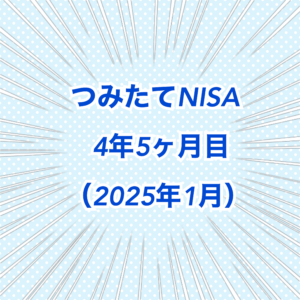
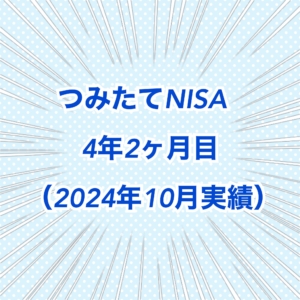
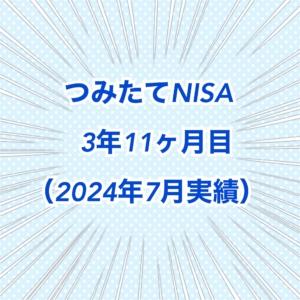

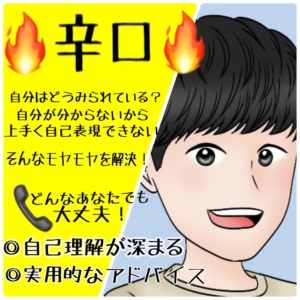



コメント